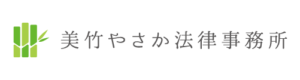簡易生命保険(通称「簡保(かんぽ)」)は、国営の生命保険でした(廃止された簡易生命保険法2条)。2007年10月1日に実施された郵政民営化でこの保険の新規契約は廃止されましたが、日本政府による保証を継続させるため、「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(郵政管理・支援機構)」に承継されました。民営生命保険である「かんぽ生命保険」を販売することとなった会社は、「かんぽ」は扱わないにもかかわらず「株式会社かんぽ生命」という会社名であって紛らわしいので注意を要します。
旧制度の「簡易生命保険契約」及び民営化後の「かんぽ生命保険契約」は、通常の生命保険契約とは異なり、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)などの各種年金と同様な「遺族制度」を採用しています。そのためか遺産分割についての実務書では、簡易生命保険契約やかんぽ生命保険契約についての記述は殆ど見つかりません。
簡易生命保険契約及びかんぽ生命保険契約の遺族制度について、株式会社かんぽ生命作成の「相続のてびき 2024年4月期」には、次のような説明があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
遺族制度はこれらの生命保険契約独自の制度で約款に規定があります。
死亡保険金受取人が無指定(コラム作成者注:被保険者死亡前に指定保険金受取人が死亡していて受取人未指定のままになっている場合を含む)の場合は、被保険者の親族を第1から第8順位に分け、先順位の遺族がいるときは次順位の者は保険金請求権を持ちません。
第1順位は内縁を含む配偶者、第2順位以下、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、被保険者の扶助によって生計を維持していた者、被保険者の生計を維持していた者となりま
代襲相続と同様な制度はありません。
(コラム作成者注:かんぽコールセンターの説明では、同順位の遺族が複数いるときは、全員協議で定めた代表者からの請求でその代表者に保険金全額が支払われ分配はその遺族間の協議による、代表者が決まらない限り支払はしない、代表者を決める手段は協議しかない、消滅時効は5年だが時効を援用することとは殆どないとのことです。相続構成ではないので遺産分割調停、審判で決めることはできず、民法427条所定の均等分割債権であるとして民事裁判手続によることになるでしょう)
簡易生命保険契約の場合、遺族に該当する者がいないときは、当該保険金は他の加入者の配当原資に当てられます。
かんぽ生命保険契約の場合、死亡保険受取人が被保険者より前に死亡して無指定状態になっていた場合、被保険者の遺族が保険金請求権を持つのは簡易生命保険と同じですが、この遺族に該当する者がいないときは、指定されていた死亡保険金受取人の法定相続人が受取人になります。
(コラム作成者注:かんぽコールセンターの説明では同順位の法定相続人が複数いるときは、全員協議で定めた代表者からの請求でその代表者に保険金全額が支払われ分配はその法定相続人間の協議による、これらの協議が整わない場合、遺産分割調停、審判で定められた請求権者からの請求があれば支払うとのことでした。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一般の生命保険の場合は、指定した保険金受取人が死亡していた場合は保険金受取人の相続人全員が保険金受取人とされている(保険法46条)のとは異なっています。
ただ同法では相続割合についての定めがないので民法427条所定の均等分割債権となるとの解釈もありえますし、その旨の裁判例もあるようですが、具体的には個々の契約条項ないし約款の定めによることになると思われます。
ある保険会社コールセンターの回答では、基本は相続人代表者に一括して支払われるが代表者が決まらないときは相続割合ではなく頭割り均等分割債権として扱うことになるのではないかということでした。